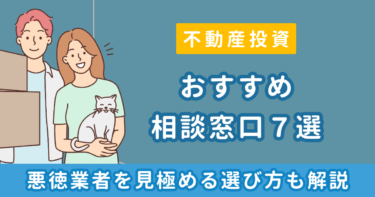「不動産投資で、家賃による安定的な収入が欲しいけれどリスクが心配…」と悩んでいませんか。
「不動産投資はリスクが高いからやめておけ」といった声も見受けられるため、不安になる方は多いでしょう。
結論から伝えると、不動産投資のリスクは未然に防げるものが多く、対策をすれば成功率が高まります。
本記事では不動産投資のリスクが高いといわれる理由や、失敗を回避する方法について紹介します。
不動産投資に伴うリスクや、メリットについて詳しく解説しているため、投資物件の購入を検討している方はぜひ参考にしてください。
不動産投資はリスクが高い・やめとけといわれる理由

不動産投資のリスクが高いといわれる理由は4つあります。
- 自然災害など予測できないリスクがある
- 大規模な修繕が必要になる
- ローンの返済が長期化する
- 悪質な不動産業者のカモにされる
不動産投資をはじめたいけれどリスクが心配な方は、ぜひ読んで役立ててください。
自然災害など予測できないリスクがある
不動産投資には、空室が増えて家賃収入が減少してしまったり、災害被害を受けたりなど、さまざまなリスクがあります。
とくに自然災害によるリスクは予測しにくいため、「不動産投資はやめておけ」といったような意見が見受けられます。
ですが不動産投資には、事前に備えられるリスクが多いです。費用を準備したり、入念に下調べをしたりなど、対策しておくと失敗を回避できる可能性が高まるでしょう。
なお、COZUCHIなら投資対象の物件選定をプロが実施するため、物件に関するリスクは抑えることができます。過去に元本割れが発生しておらず、最小で1万円から始められるため、損失を出しにくいと考えられます。
大規模な修繕が必要になる
不動産投資のリスクが高いとされる理由のひとつに、アパートやマンションで発生する大規模な修繕があります。
大規模修繕とは、経年劣化に伴う不具合を予防するためにおこなわれる工事です。
建物の規模や種類により異なりますが、1回の工事で数十万~数百万と多額な費用がかかります。
そのため計画的に修繕費用を積み立てておく必要があります。
しかし修繕費用の積み立てがないと、大規模修繕の際に大きな借金ができるため、リスクが高いと言われています。
ローンの返済が長期化する
投資物件のアパートやマンションは、1棟まるごと購入するケースが多いです。
取引する額が1,000万以上と大きく、ローン返済が10~20年と長期化するためリスクが高いといわれています。
不動産投資はレバレッジがかけられるため、手持ちの資金が少なくても契約が可能です。
しかし自己資金が少ないほど、金利が高くなり返済金額が増えてローンが長期化し、リスキーな不動産投資になります。
悪質な不動産業者のカモにされる
残念なことに、不動産業界には詐欺まがいの業者も存在します。
悪質な不動産業者にあたってしまうリスクもあるため、不動産投資はやめとけと言われる理由の1つです。
特にサラリーマンは安定した収入があり、ローン審査に通過しやすく、狙われやすいので注意が必要です。
さきほど述べたような、高額なマンションを無理に購入させられたり、必要な修繕を隠して築古物件を売りつけられる。購入を急かす業者もいるため、注意が必要です。
不動産投資における8つのリスクと対策
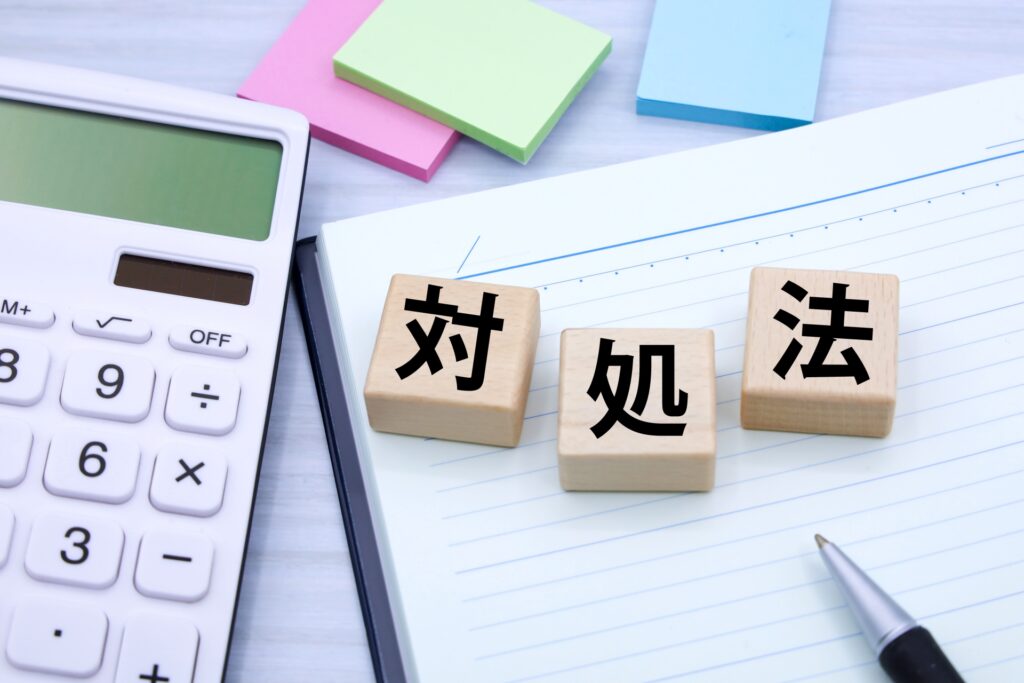
不動産投資で発生する8つのリスクは、下記のとおりです。
- 空室リスク
- 不動産価格の下落リスク
- 家賃の下落リスク
- 金利上昇のリスク
- 家賃滞納リスク
- 修繕リスク
- 災害リスク
- 倒産リスク
リスクの詳しい内容と、それぞれの対策を紹介するため、不動産投資を検討している方はぜひ参考にしてください。
空室リスク
不動産投資には空室リスクがあります。
引越しで空室が増えたり、新しい入居者が決まらず空室が長期化したりするとローン返済に影響が出るため、早めの原因分析と対策が必要です。
空室が増える要因は、下記のとおりです。
- 周辺エリアの人口が減少している
- 相場より家賃が高い
- ライバル物件と比べて設備が古い
- 入居同士のトラブルが多い
- ロビーやゴミ置き場といった共用部分の管理状態が悪い
空室リスクを避けるために、地域の人口減少率を調査したり、物件の周辺エリアにコンビニやスーパーなどの施設があるか調べたり、事前の調査を入念におこないましょう。
周辺エリアの相場より家賃が高い場合や、家賃が築年数や設備に見合わないと、入居者がライバル物件に流れてしまいます。
周辺エリアの家賃相場を分析したり、便利な宅配ボックスの導入やセキュリティ強化など設備投資をしたりして、空室リスクに備えましょう。
また空室率を増加させないために、入居者に長く住んでもらえるよう、満足度を上げるのも重要です。
たとえば騒音や汚部屋など入居者トラブルに対する早め対応や、共用部を清潔に保つための管理など、心地よく住めるような環境づくりが必要です。
不動産価格の下落リスク
不動産投資には、物件自体の価値が落ち、価格が下落して損失が出るリスクがあります。
不動産価格が下落する3つの要因は、下記のとおりです。
- 少子高齢化に伴う人口減少による供給の増加
- 団塊世代の高齢化による不動産相続や売却の増加
- 住宅ローンに関する金利の上昇
少子高齢化に伴い住人が減少しているため、供給が上回り不動産の価値が下がります。
今後は団塊世代が高齢化し相続が増えるため、不動産の数が増加し、価格の下落をさらに悪化させると予想されています。
利便性が高く若者が集まりやすい都心部や、人口増加がみられる地域の物件であれば、需要が高いため不動産価格の下落のリスクヘッジが可能です。
そのほか住宅ローンの金利が上昇すると返済費用が増えるため、不動産購入の需要が減少する可能性があります。
こちらについては、のちほど「金利上昇リスク」で詳しく紹介します。
家賃の下落リスク
不動産投資には、家賃の下落リスクがあります。
家賃が下落する原因は下記のとおりです。
- 周辺エリアの人口の減少
- 似たような設備を備えた同じ価格帯の物件の増加
- 空室の長期化
- 経年劣化
- 築年数の増加
家賃の下落リスクを防ぐには、暮らしやすく利便性のある需要の高いエリアを選んだり、ほかの物件との差別化をはかる必要があります。
ターゲット層にあわせてリフォームやリノベーションをおこない、人気の間取りにしたり設備を充実させたりして、物件の魅力を高めましょう。
また経年劣化による設備老朽化に伴う家賃の低下は、計画的な大規模修繕の実施により防げます。
家賃水準を保ち収入を落とさないために、大規模修繕は定期的におこないましょう。
金利上昇リスク
不動産投資には、政府の金融施策により金利が上がり、購入意欲が低下するリスクがあります。
住宅ローンの金利が上昇すると、不動産取得の需要が減少するため、不動産価格が下落する恐れがあります。
不動産投資を検討している方は日本の経済状況や、政府が打ち出している金融施策について、随時チェックし対策しましょう。
家賃滞納リスク
不動産投資には、入居者の家賃滞納リスクが伴います。
家賃を滞納されると自身の収入が減少するうえ、長期化するとローン返済にも影響が出るため、早めに対処しないと危険です。
とはいえ家賃滞納による立ち退き要請には、3か月以上の滞納実績が必要なため、すぐには退去してもらえません。
そのため家賃滞納のリスクは、入居前の事前の対策が重要です。
また家賃滞納者の立ち退きを要請をするためには、訴訟を起こすため裁判費用や弁護士費用が必要になり、さらに出費が増えてしまいます。
家賃滞納のリスクを回避するためには、下記の対策が有効です。
- 入居審査を徹底している管理会社を選ぶ
- 入居者に連帯保証人をつける
- 家賃保証会社に加入してもらう
- 家賃の支払いをカード払いや自動引き落としにする
家賃を滞納する可能性が高い、支払い能力の低い方を入居させないよう、審査を厳しくしている管理会社を選びましょう。
入居者に連帯保証人をつけたり、保証会社に加入してもらったりなど、家賃が支払われない場合に保証される制度の利用で、家賃滞納のリスクに備えられます。
また家賃の支払いをクレジットカード払いや、自動引き落としにすると、入金漏れによる家賃滞納を防げます。
修繕リスク
不動産投資には修繕が必要となる場面が多く、出費が増えるリスクがあります。
建物は年数が経つにつれて、設備がどんどん劣化していくため、メンテナンスとして修繕工事が必要です。
経年劣化による修繕には、下記のような工事があります。
- 屋上防水工事
- 外壁塗装工事
- 給湯設備や排水設備の交換工事
さらに経年劣化による修繕工事を実施していたとしても、入居者による設備の破損や不具合が起きる場合があり、そのたびに工事が必要です。
修繕リスクに備えるための対策は、下記の3つが挙げられます。
- 突発的な故障や不具合に対応できるよう修繕費用を積み立てておく
- 退去時に原状復帰できるよう敷金を設ける
- 投資物件を探すときに修繕履歴を確認しておく
修繕費用は余裕をもち、積み立てておくと突然の出費に対応ができます。
自身による修繕費用の積み立てが難しい場合は、管理会社に代理で積み立てを依頼しましょう。
家賃を管理するときに一定の金額を積み立てられるため、自身で管理する手間が省けて効率よく備えられます。
中古物件を購入する際は、定期的な大規模修繕がおこなわれていたか、修繕工事の履歴を確認しましょう。
メンテナンスされてきた物件を選べば、設備の老朽化に伴う突発的な不具合が起こりにくく、修繕リスクが抑えられます。
災害リスク
不動産経営には、地震や大雨といった災害により、物件の価値が下がる災害リスクが伴います。
とくに自然災害は予測して避けるのは難しいため、被災したときのために備えて準備しておきましょう。
災害リスクに備えるための対策を3つ紹介します。
- 火災保険や地震保険に加入する
- 新耐震基準を満たしている物件を選ぶ
- 耐震工事をおこなう
- ハザードマップで被災が想定される区域を確認する
災害保険に加入すると、火災や地震で被害を受けた場合に、復旧のために必要な費用を補償してもらえるため、自己資金の損失の回避が可能です。
新耐震基準を満たしている物件の検討や、耐震工事の実施により、地震による被害を抑えられます。
新耐震基準とは、震度6強~7程度の揺れを受けても家屋が倒壊しないように定められた耐震基準です。
1981年6月1日に施行された法令で、築年数40年以内の建物であれば、新耐震基準が適用されています。
国や市町村が提供しているハザードマップは、地震や津波といった災害の種類ごとに作成されており、被害を受けやすい地域の確認が可能です。
被災のダメージを大きく受ける地域を避けて、物件の検討を進めていくと、災害リスクを軽減できます。
倒産リスク
不動産投資には、ローンの返済が滞り自己破産へ追い込まれてしまう、倒産リスクがあります。
不動産経営では多額のローンを組む必要があり、収支計画を見誤り破産するケースが見受けられます。
倒産リスクを回避するため、下記に気をつけてみてください。
- 修繕費用やリフォーム代といった支出費用の見通しを細かく算出する
- フルローンやオーバーローンは避ける
- できれば物件価格の15~30%の自己資金を用意しておく
不動産経営には修繕費のほか、リフォーム代や固定資産税などさまざまな費用がかかります。
経営していくうえで必要な経費を細かく算出し、綿密に投資計画を練りましょう。
住宅ローンを組む際にフルローンや、自己資金なしで物件を購入できるオーバーローンといった高金利のローンは避けたほうが無難です。
銀行からの借入額が増えるほど、月々の返済額が高額になるため、倒産のリスクが高くなります。
また不動産を購入する際は、物件価格の15~30%の自己資金の用意が望ましいでしょう。
頭金や不動産会社への仲介費用といった初期費用を準備すると、オーバーローンを避けられ銀行から受ける融資の金額が下げられます。
本記事で紹介しているさまざまなリスクが重なり、思わぬ出費が増えるとローン返済が難しい状態に陥るケースも考えられます。
ひとつひとつのリスクと対策を理解し、備えることで倒産のリスクを回避が可能です。
不動産投資の失敗率はどのくらい?失敗した人の末路は?

不動産投資は失敗率が高い=リスクがあるとよく言われます。
特に初心者は、適切な知識や計画がないまま投資を始め、思わぬ損失を被ることが多いです。
失敗率と、失敗した人の末路についての詳細を解説していきます。
失敗率90%!成功率たったの10%という説もある
不動産投資は90%の人が失敗すると言われることもあります。この数値だけだと、成功確率はとても低いように感じてしまうかもしれませんが、これは一部のデータに過ぎません。
不動産投資は確かに簡単ではありませんが、しっかりとした知識と準備があれば成功する可能性は十分にあります。
失敗する理由の多くは、初心者が知識不足で無計画に投資を始めることが原因です。逆に、成功者は長期的な視点を持ち、リスクを理解し、慎重に計画を立てています。
不動産投資の魅力は、キャピタルゲイン(売却益)とインカムゲイン(賃貸収入)の両方が得られる点です。不動産投資で成功するためには、両者をバランスよく追求することが大切です。
長期的な視点では、安定したインカムゲインが重要です。毎月の家賃収入はローン返済や維持費をカバーし、安定したキャッシュフローが実現します。
一方、キャピタルゲインは物件の売却時に得られる一時的な利益です。市場の動向を把握し、売却のタイミングを見計らうことで大きな利益を得ることができます。
しかし、短期的な利益を追求するだけでは、長期的な成功は難しいでしょう。
失敗した人の末路は?失敗例を紹介
| 不動産投資の失敗例 | |
|---|---|
| 赤字運営 | 購入した物件が思ったほど収益を上げられず、毎月の収支が赤字に。自分の資金を投入せざるを得ない状況に追い込まれる。 |
| 売却困難な物件 | 市場価値が低く、誰も買いたがらない物件を持ち続けることに。管理や修繕の手間とコストが重荷になる。 |
| 違法行為のリスク | 知らないうちに不正に加担し、法的問題に発展。借り入れを一括返済するよう求められるケースもある。 |
不動産投資に失敗すると上記のような末路をたどってしまう可能性があります。
たとえば、キャッシュフローが赤字になり、毎月の支出が増えるケースです。物件が売れないまま管理費用がかかり続けることも少なくありません。
さらに、違法行為に巻き込まれると、融資を一括返済する事態も考えられます。
不動産投資のリスクについての十分な知識・信頼できる業者選び・慎重な投資計画がなによりも大切です。
デメリットばかり?不動産投資のメリットは?

不動産投資のメリットは、下記の4つが挙げられます。
- 不労所得を得られる
- レバレッジ効果が高い
- 節税効果がある
- 生命保険に加入できる
不動産投資はリスクが多いですが、デメリットばかりでなくメリットもあります。
不労所得を得られる
不動産を購入すると、入居者から毎月家賃が支払われるため、不労所得が実現するところがメリットです。
不動産投資により、自身が働かなくてもお金を得られる仕組みが手に入ります。
家賃収入を安定させ多くの収入を得るために、空室や家賃下落のリスクがある物件は避けましょう。
レバレッジ効果が高い
不動産投資はレバレッジ効果が高く、多くの収入を得やすい点が強みです。
不動産経営におけるレバレッジとは、少ない自己資金と銀行からの融資をあわせて投資し、自己資金のみでは得られなかった大きな利益が期待できる仕組みをいいます。
銀行からの借入もプラスして投資ができる点が、株式投資にはない不動産投資特有のメリットです。
節税効果がある
本業と並行して不動産経営をしている場合、所得税や住民税の節税対策ができます。
不動産経営では管理費や修繕費といった、さまざまな費用を経費として計上できるため、所得税や住民税が軽減されます。
不動産投資による節税対策は、課税所得が900万を越える方におすすめです。
累進課税制度により、所得が多いほど税金の額が多くなるため、不動産投資により経費を計上すると、課税所得が減少し節税できる金額が大きくなります。
生命保険に加入できる
投資物件を購入する際、多くの場合「団体信用生命保険(団信)」と呼ばれる生命保険に加入します。
万が一の事態に備えて加入する保険で、契約者が亡くなったとしても団体信用生命保険により、保険会社から金融機関へお金が支払われます。
ローンが完済されれば、無借金の不動産資産として家族に残せるところが強みです。
ただし団体信用生命保険では不動産資産を残せますが、生命保険(死亡保険)のように現金は手に入りません。
そのため家賃収入のみでは生活が厳しい場合や、不動産経営が上手くいかない場合は、家族に負担がかかります。
上記のように団体信用生命保険は、完全に生命保険の代わりにはなるわけではありません。
2つの保険の違いを理解し、不足を補う必要があれば生命保険の加入を検討しましょう。
不動産投資におけるリスクを回避!成功率を上げるポイント

不動産投資で起こるリスクや失敗を回避する方法には、下記の6つがあります。
- 立地・周辺の情報を集める
- 建物の状態を確認する
- 空室リスクの高い物件は避ける
- 収支のシミュレーションをする
- 自己資金を準備しておく
- 悪徳業者でないかを見極める
失敗するリスクが高い物件を契約してしまわないよう、調査が必要な情報や、自己破産を防ぐ収支計画の立て方について紹介します。
立地・周辺の情報を集める
不動産投資の失敗を避けるため、物件を購入する際は立地や周辺エリアの情報など下調べをおこないましょう。
投資物件を購入する際に調べたほうがよい情報は、下記の通りです。
- 周辺エリアの人口減少率
- 最寄り駅のアクセスのよさや周辺施設の充実度などの暮らしやすさ
- ターゲット層
- 周辺エリアの新築物件やライバル物件の設備
検討中の物件のエリアの人口推移や、付近のショッピングモールや病院といった周辺情報を入念にチェックしましょう。
人口が増えている傾向がみられる地域や、そのエリアの住人の暮らしやすさを重視した物件を選ぶと、不動産価格や家賃の下落リスクと、空室が長期化するリスクの回避につながります。
建物の状態を確認する
物件を購入する前に、建物の修繕履歴や耐震状況は必ず確認しましょう。
とくに中古物件を購入する場合は、定期的に修繕がされていない物件を選んでしまうと、購入後すぐ工事が必要になる可能性があり、大きな出費が出てしまいます。
古い物件であれば、過去にリフォームやリノベーション工事がされているかもあわせて確認するのをおすすめします。
ターゲット層に需要がある設備を整えているか、また周辺エリアのライバル物件と比べて設備に劣りはないかなどを調べてみましょう。
ターゲット層に人気な設備や間取りで、ライバル物件との差別化ができれば、空室リスクや家賃下落のリスクに備えられます。
空室リスクの高い物件は避ける
投資物件を検討する際は、空室リスクが高い物件は避けましょう。
空室が長期化すると収入が減少し、ローン返済にあてられるお金が少なくなるため危険です。
空室リスクが高い物件は下記のとおりです。
- 周辺に新築物件が増えている
- 年々人口が減少している地域の物件
- 築年数が古い
周辺エリアに新築物件やライバルとなるような類似物件が増えると、空室が増えたり家賃を下げたりしないと入居者が決まらないといった状況に陥ります。
またエリアの人口が減少傾向にある地域の物件も、入居者の取り合いになる可能性が高いため、おすすめはできません。
上記のような物件の購入は避け、不動産投資の失敗を回避しましょう。
収支のシミュレーションをする
不動産投資における収支シミュレーションとは、返済や費用などの支出と、将来得られる収益を具体的な数字に落とし込んだものです。
収支シミュレーションで算出可能なデータは、下記が挙げられます。
- 金利を含めた返済総額
- 年間の家賃収入
- 年間の諸経費
- 年間の手取り金額
- 利回り
収支シミュレーションは、不動産投資のリスクを確認するために欠かせないものです。
具体的な金額が算出されるため、より緻密な投資計画が立てられます。
なお「収支シミュレーションは不動産会社がしているから」と提示されたものを、そのまま鵜呑みにするのは危険です。
自身で情報を集め、家賃の下落リスクや空室のリスクを考慮しながら、複数のパターンによる入念なシミュレーションをしてみてください。
収支シミュレーションに必要な物件情報は下記のとおりです。
- 物件価格
- 想定の家賃収入
- 想定の空室率
- 自己資金額
- 借入金額
- 借入期間
- 金利
収支シミュレーションによりリスクを見える化し、不動産投資によるリスクに備えましょう。
自己資金を準備しておく
不動産経営には、予測できないリスクがいくつもあるため、突然の出費にも対応できるよう、自己資金はできる限り多く準備しておきましょう。
自己資金なしで不動産投資に挑戦するのは可能ですが、返済が高額になるため倒産のリスクが上がります。
金利が高くなる高額なローンを組まずに済むよう、余裕をもった自己資金の積み立てをおすすめします。
物件契約時に必要な頭金はもちろん、不測の事態に備えて自己資金を多く用意しておくほど、リスクの少ない不動産投資が可能です。
また頭金をより多く準備しておくと、ローンの審査が通りやすくなるため、目当ての物件を購入しやすくなります。
悪徳業者でないかを見極める
不動産投資界隈の悪徳業者に騙されると、高額な損失を被ってしまいます。リスク回避のためにも信頼できる業者かどうかはしっかり見極めておく必要があります。
まずは過去の取引実績や実際にその業者を利用した知人や同僚からの情報を参考にしましょう。
そして、契約内容をしっかりと確認します。
特に、サブリース契約の場合、契約書に記載された家賃保証の期間や条件を詳細にチェックしましょう。家賃保証が長期間にわたる場合でも、更新時に家賃が大幅に下がる可能性があるため、注意が必要です。
また、業者の営業担当者が物件のメリットだけでなく、リスクについての説明があるかどうかも重要です。
リスクを隠したり、過度に楽観的なシミュレーションを提示する業者は避けておいたほうが良いでしょう。
これらのポイントを押さえることで、悪徳業者を見極め、不動産投資の成功率を大幅に上げることができます。
不動産投資のリスクに関するよくある質問

最後に不動産投資のリスクについて、よくある6つの質問に回答します。
- 不動産投資の最大のリスクは何ですか?
- 不動産投資は儲からない(割に合わない)のですか?
- 不動産投資をやっている人の割合はどのくらいですか?
- 不動産投資に役立つ資格は?
- 何年で収支はプラスになりますか?
- 確定申告しないとどうなる?
不動産に関する資格の必要性や、初期費用の回収期間などひとつずつ詳しく紹介します。
不動産投資最大のリスクは何ですか?
不動産投資の最大のリスクは、空室リスクです。
賃貸物件に空室が生じると、家賃収入が途絶え、ローンの返済や維持費の負担がオーナーにのしかかります。
特に人口減少や地域の賃貸需要の低下が進むエリアでは、このリスクが顕著です。
空室リスクを最小限に抑えるためには、賃貸需要の高い地域、例えば東京などの都心部に物件を購入することが有効です。
また、入居者募集に強い賃貸管理会社を選ぶことも重要です。
不動産投資は儲からない(割に合わない)のですか?
不動産投資が「儲からない」と言われる理由の一つは、短期間で利益を得るのが難しい点です。
不動産投資は長期的な視点で取り組むことが必要で、キャピタルゲインやインカムゲインを得るには時間がかかります。
しかし、適切な物件選定や投資戦略を持っていれば、収益を上げることは可能です。
成功している投資家の多くは、綿密なリサーチとリスク管理を行い、賃貸需要の高いエリアや物件を選んでいます。
不動産投資をやっている人の割合はどのくらいですか?
日本における不動産投資経験者の割合は調査によって異なりますが、一般的には10%〜20%程度とされています。
国土交通省が実施した「平成30年度不動産投資に関する意識・行動調査」では、不動産投資を経験したことがある人の割合は12.6%でした。
また、特定の層に焦点を当てた別の調査では、サラリーマンのうち61.06%が不動産投資を行っているという結果も報告されています。
不動産投資に役立つ資格は?
不動産投資に役に立つ資格は、下記のとおりです。
- 宅地建物取引士
- 賃貸不動産経営管理士
- マンション管理士
- 管理業務主任者
- ファイナンシャル・プランナー技能士
不動産投資をして大家さんになるために必須の資格ではありませんが、投資物件を検討する際や不動産経営をしていくうえで役に立ちます。
不動産投資によるリスクや失敗を回避したい方は、資格勉強での専門知識習得がおすすめです。
何年で収支はプラスになる?
不動産投資による初期費用の回収期間は、物件の種類により異なりますが約5~10年です。
たとえば新築アパートの場合、購入価格は高いうえ高額の家賃設定が難しいため、利回りが低く回収期間が長引く傾向にあります。
反対に中古アパートの場合は、新築と比べると安く購入が可能です。
空室リスクの少ない物件であれば利回りもよく、回収期間が短くなるケースがあります。
そのほかマンションかアパートか、1棟か区分かなど、条件により回収期間は大幅に異なるため、それぞれの特長にあわせて無理のない投資計画を立てましょう。
確定申告しないとどうなる?
不動産投資により得た収入を確定申告しなかった場合、本来納めるべき金額の納税と罰金が課せられます。
確定申告を怠った場合のデメリットは、下記のとおりです。
- 収入証明の書類がなくなる
- 青色申告ができなくなる
- 融機関の信頼を失い融資が受けられなくなる
- 5年以下の懲役または500万以下の罰金が課せられ前科がつく
確定申告を怠ると「お金にルーズ」といった印象がついてしまい、銀行から融資が受けられなくなります。
さらに悪質な脱税行為だとみなされると、最悪の場合は前科がつき社会復帰すらも厳しくなります。
金融機関への印象を悪くしないように、確定申告は必ずおこないましょう。
まとめ

不動産投資にはリスクが多いですが、突発的な出費に備え充分な自己資金を準備したり、購入前の調査を徹底的におこなったりなど対策をすれば、失敗は回避できます。
不動産投資は取引する金額が大きいため、物件購入の検討は慎重に進めましょう。
複数のリスクを想定した入念な収支シミュレーションをおこなえば、返済が滞るリスクを抑えた不動産経営が可能です。
本記事で紹介したリスク対策を参考にして、利益が得られる不動産投資を目指してみてください。