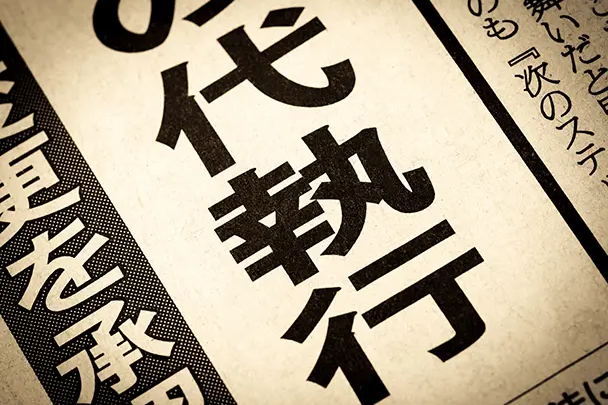空き家を放置する危険性と対策ガイド
- 更新日:2025.11.10

近年、少子高齢化や人口減少の影響で空き家の数が大きく増えています。
都市部と地方の人口格差は広がり、所有者の高齢化などからも空き家の管理が滞る傾向が進んでいるのが現状です。
このような背景のもと、空き家はさまざまなリスクを抱えており、社会的にも大きな問題となっています。
空き家を放置してしまうと、建物の安全性が損なわれて倒壊の危険が高まるほか、不法侵入や放火などの犯罪リスクも高まる可能性があります。
また、害虫・害獣の発生による衛生面の悪化や、周囲の景観や資産価値の低下といった影響も見過ごせません。
本記事では、空き家に関する法的な定義やリスクの具体例を取り上げながら、放置を避けるための対策・活用方法を詳しく解説していきます。
さらに、行政による指定制度や所有者の法的責任についても触れ、空き家管理の重要性と早期対応の必要性を分かりやすく紹介します。
実際にあなたが所有する空き家をなんとかしたいのであればタウンライフ空き家解決の利用がおすすめ。
たった60秒の情報入力で、空き家に関する診断だけでなく、複数の優良業者から空き家の解決プランを無料で手に入れることができます。
空き家のお悩みは
タウンライフでまるごと解決!

\かんたん1分!ベストな空き家解決策とは?/
空き家の現状と背景

まずは空き家が増加している社会的背景と、その要因を確認します。
少子高齢化が進む日本では、若年層の人口が減っていく一方で高齢者の割合が増え、結果として使われなくなった家屋が増え続けています。
都市部への人口集中や就職・進学に伴う地方離れも、住宅の空き家化を加速させる要因のひとつです。
所有者が遠方に住んでいる場合や相続で受け継いだものの管理が難しい場合は、そのまま放置されるケースが少なくありません。
こうした空き家の増加は、行政が管理や対策にかかるコストを負担しなければならない社会問題へと発展しています。
景観の悪化や治安上のリスクの増加、地域コミュニティの衰退など、さまざまな面で深刻な影響を及ぼします。
空き家増加の要因と社会問題化
主な要因としては、過疎化や少子高齢化による人口減少、そして都市部への一極集中が挙げられます。
地方では働き口が限られるために若い世代が流出し、実家や親族宅が無人になる事例が増加し続けているのです。
使われない住宅は固定資産税などの出費を生みながらも市場価値を失いやすく、管理負担や治安面でのリスクが深刻化しています。
空き家とは?法的定義と判断ポイント

法律上の空き家の定義や、実際に空き家に該当するか判断する際のチェックポイントを見ていきましょう。
空き家対策特別措置法では、居住その他の使用がなされていない建物や敷地を大まかに空き家と定義しています。
ただし、季節的な利用や一時的に留守の住宅などは空き家に該当しない場合があります。
電気・ガス・水道の使用状況や郵便物の集配状況、長期間の人の出入りの有無が判断の重要ポイントです。
また、物理的な外観や建物の老朽化具合も空き家かどうかの見極めには重要になります。
建物の傷みが明らかで居住の形跡がない場合は、管理の有無を至急確認しましょう。
万一、管理が行われていなければ、法的な空き家とみなされる可能性が高くなります。
空き家を放置する7つのリスク

空き家を長期間放置してしまうと、さまざまなリスクが生じます。
代表的な7つの事例を解説します。
※各項目をクリックすると詳細にジャンプします。
- 建物老朽化・倒壊による周囲への危険
- 治安悪化や不法侵入、放火の可能性
- 害虫・害獣の発生や不法投棄
- 街の景観を損ねると同時に資産価値が下がる
- 固定資産税や維持管理費の負担増
- 特定空き家指定による行政処分のリスク
- 事故や災害発生時の損害賠償責任
1. 建物老朽化・倒壊による周囲への危険
木造住宅などは特に劣化が進みやすく、定期的に人が住んでいない空き家は雨漏りやシロアリ被害などで急速に老朽化します。
地震や台風などの災害時には倒壊リスクが高まり、倒壊した建物が近隣の住宅や通行人に被害を及ぼすこともあります。
所有者には重大な賠償責任が発生する可能性があり、早期の修繕・点検が必須です。
2. 治安悪化や不法侵入、放火の可能性
人目が少なく管理が行き届いていない空き家は犯罪の温床になりやすいとされています。
放置されている建物は火の不始末や放火の狙いどころとなり、地域全体の治安悪化につながることも少なくありません。
不法侵入者が居座ると、ゴミ散乱や暴力行為など周辺被害が拡大します。
3. 害虫・害獣の発生や不法投棄
空き家は長期間掃除や衛生管理が行われないため、ゴキブリやネズミなどの害虫・害獣が繁殖しやすい環境になります。
さらに、人目が少ない場所には不法投棄が起こりやすく、ゴミや残飯が放置されると悪臭や衛生問題が深刻化しやすくなります。
衛生悪化は近隣トラブルに直結し、地域環境の悪循環を招きます。
4. 街の景観を損ねると同時に資産価値が下がる
管理されていない荒れ果てた建物は街の景観を大きく乱すため、住環境や地域ブランドの価値を低下させます。
結果として、近隣の住宅や土地の資産価値にも悪影響を及ぼし、売却や賃貸の際に不利な条件となる可能性があります。
景観悪化は地域経済にも波及し、空き家の増加を助長します。
5. 固定資産税や維持管理費の負担増
空き家であっても固定資産税や都市計画税などの税金は支払い義務があり、放置している間にもコストがかかり続けます。
さらに建物が老朽化すると修繕費用が高くつき、必要な手入れを怠ると費用がかさむ一方になりがちです。
使っていない建物への継続的な出費は家計を圧迫します。
6. 特定空き家指定による行政処分のリスク
周囲に危険を及ぼすような状態の空き家は、特定空き家として行政から指定される場合があります。
指定後は行政からの勧告・命令を受け、改善措置を取らなければ強制解体や費用の徴収といった厳しい処分が下されることもあるのです。
命令に従わない場合、代執行と費用徴収が実施される可能性があります。
7. 事故や災害発生時の損害賠償責任
老朽化による倒壊や火災、不法侵入者による事故などが発生した場合、空き家の所有者は損害賠償責任を問われる可能性があります。
これは民法の規定に基づき、工作物責任が適用されるケースがあるためです。
大事故は多額の賠償金につながるため、放置は極めて危険です。
空き家のお悩みは
タウンライフでまるごと解決!

\かんたん1分!ベストな空き家解決策とは?/
特定空き家の指定とは?

空き家の中でも特に危険性が高い場合、特定空き家として指定されます。
その定義や指定された場合の流れを解説します。
※各項目をクリックすると詳細にジャンプします。
特定空き家の定義と指定条件
法令では、建物の倒壊や重大な不具合が近隣に危害を及ぼす可能性がある場合などを特定空き家の条件としています。
また、害虫やゴミの放置による感染症リスクが増すなど、衛生環境の悪化が明白な場合も対象になることがあります。
自治体は現状調査を経て、正式に特定空き家として指定します。
特定空き家に指定されるとどうなる?
指定されると最初に行政から勧告や指導が行われ、空き家の改善に向けた具体的措置を求められます。
所有者がこの段階で修繕や解体などの対応をすれば、事態は比較的軽度に収まる場合が少なくありません。
指示を無視すると行政命令を経て代執行が行われ、費用は所有者負担になります。
空き家対策特別措置法における罰則と権限
空き家対策特別措置法では、自治体に立入調査や勧告・命令の権限を与え、問題のある空き家に強制的な対応を取ることを可能にしています。
所有者がそれに応じない場合、自治体は代執行を行い、解体費用や撤去費用を請求することができます。
深刻化する前に対策を講じることが、最終的な負担を小さくします。
所有者の法的責任と損害賠償

空き家の所有者には、万一の事故や被害における法的責任が問われるケースがあります。
具体的な根拠と事例を見てみましょう。
※各項目をクリックすると詳細にジャンプします。
工作物責任(民法717条)の概要
民法717条では、建物や塀、看板などを含む『工作物』の設置や保存に瑕疵があった場合に、所有者が損害賠償責任を負うと規定しています。
空き家は誰も住んでいないからといって、この規定から逃れられるわけではありません。
点検や補修の怠慢は、事故時に厳しく責任追及される可能性があります。
火災・倒壊事故時に発生する賠償義務
老朽化した屋根や壁が崩落し、通行人がケガを負ったり、隣家に被害が及んだりすると、法的には所有者の不法行為責任が問われます。
また、老朽化した電気配線などから火災が発生し、周囲に延焼した場合も同様です。
事故は一瞬で大損害に発展するため、予防的メンテナンスが最も重要です。
事故の具体的事例と判例
実際の裁判例では、外壁が落下して通行人が重傷を負ったケースや、空き家の一部が崩れて車両を破損したケースで、数百万円から数千万円規模の損害賠償が認められた例が存在します。
また、放火により全焼した空き家が隣接する建物にも被害を広げた場合、所有者の放置責任が問われた事案もあります。
判例は、管理不足が高額賠償に直結することを示しています。
空き家のお悩みは
タウンライフでまるごと解決!

\かんたん1分!ベストな空き家解決策とは?/
空き家の管理方法と予防策
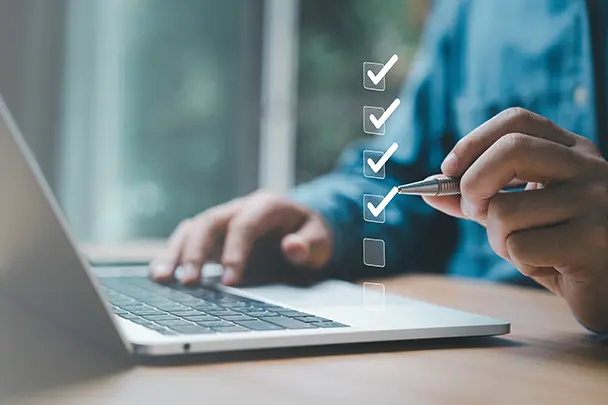
空き家を安全かつ衛生的に保ち、周囲のトラブルを防ぐための管理ポイントを押さえておきましょう。
空き家の管理では、定期的な巡回や清掃、建物や設備のメンテナンスが欠かせません。
※各項目をクリックすると詳細にジャンプします。
定期的な巡回と建物メンテナンス
巡回の頻度は月に1度程度が理想ですが、長期間足を運べない場合でも、最低でも季節の変わり目などの節目ごとに点検に訪れることが大切です。
屋根や外壁のひび割れや雨漏り、基礎部分の腐食などは早期に発見すれば修繕コストを抑えられます。
内部は通気を確保し、湿気対策でカビ・害虫の発生を防ぎましょう。
害虫駆除・害獣対策と清掃管理
ゴミや落ち葉が蓄積されると、ゴキブリやネズミなどの害虫や小動物が住み着きやすい環境を作ってしまいます。
周辺の草木が繁茂している場合は定期的に草刈りを行い、掃除や消毒を徹底することで衛生害虫の侵入を防げます。
敷地外へのゴミ流出を防ぎ、近隣への配慮を徹底しましょう。
放火・漏電予防のためのチェックポイント
家財道具や紙類など、可燃物を大量に置いたままにしておくと、放火のリスクが高まります。
不要なものは整理・処分し、建物周囲に廃棄物や雑草を放置しないように心がけましょう。
電気設備・配線は専門業者による定期点検で漏電火災を未然防止。
空き家を活用するための選択肢

空き家を放置せず、有効活用することでリスクやコストを削減する選択肢があります。
空き家の状態や立地条件を踏まえて、売却や賃貸、リノベーションなどを検討することで、維持管理費や固定資産税の負担を軽減できる場合があります。
※各項目をクリックすると詳細にジャンプします。
売却・賃貸・リノベーションの検討
空き家の売却は固定資産税などの負担を一気に軽減する方法ですが、立地や築年数によっては買い手がつきにくい場合もあります。
賃貸に出す場合は、適切なリフォームで家賃収入を得ることも可能ですが、空室リスクや管理業務が発生する点を考慮する必要があります。
リノベーションで魅力を高めれば、資産価値向上と収益化が期待できます。
空き家バンクや自治体の支援制度
空き家バンクは自治体が運営している物件情報のマッチングサービスで、空き家の売主や貸主と、購入や賃借を希望する人をつなぐ仕組みです。
補助金制度やリフォーム助成金を活用することで、負担を軽減しながら物件の再生を進められるケースがあります。
地方移住促進の枠組みでは、手厚い支援が用意されていることが多いです。
自治体や専門家への相談方法

空き家の管理や活用に不安がある場合、自治体や専門家に相談するのが重要です。
空き家に関する法律や制度は複雑であり、自己判断だけでは適切な対策をとるのが難しいケースも多々あります。
そこで、自治体に設置された専門窓口やワンストップ相談窓口を利用するとスムーズにサポートを受けられるでしょう。
※各項目をクリックすると詳細にジャンプします。
空き家ワンストップ相談窓口の利用
多くの自治体では空き家に特化した相談窓口を設けており、複数の部署を跨ぐ問題を集中的に相談できる体制が整っています。
具体的には、税金や法務、建築基準など異なるジャンルの専門家と連携しているケースが多く、効率的に解決策を探せます。
初めての所有者でも、手続き案内から業者紹介まで総合支援が受けられます。
弁護士・不動産会社・行政書士などの専門家
空き家の売買や賃貸契約を検討する際には、不動産会社が市場動向を踏まえたアドバイスを提供してくれます。
また、相続問題など法的な手続きが伴う場合は弁護士の助言が必要となり、書類作成や許認可手続きは行政書士がサポートを行います。
複雑な案件ほど、適切な専門家選びと協力体制の構築が重要です。
早期対策に向けた家族・親族間の話し合い

空き家リスクを回避するためには、早めに家族・親族と協議を進めておくことが大切です。
親や祖父母が暮らしていた住宅が空き家となるケースでは、相続時期や権利関係、活用方法などをしっかり話し合っておく必要があります。
後回しにしてしまうと、急なトラブルや費用の追徴が発生するリスクが高まります。
複数親族が関与する場合は、早期の意思疎通と合意形成が円満解決につながります。
※各項目をクリックすると詳細にジャンプします。
生前対策や相続手続きの確認
親族間で共有している不動産は、相続の段階で誰がどう引き継ぐかが大きな問題になります。
生前贈与や遺言書の作成など、法的・税務的な観点から手続き方法をあらかじめ確認しておくと、将来的なトラブルを防ぎやすくなります。
空き家は資産価値が不透明なため、早期の評価と方針決定が鍵です。
実家の空き家化を防ぐための工夫
親が高齢になり、実家が空き家となりそうなタイミングでは、早期に別の活用方法や売却などを検討することが有効です。
例えば、二世帯住宅への改築や賃貸用のリフォームを行い、収益を得られる物件に変えておくことも一案でしょう。
家族で計画・役割分担・費用負担を共有し、協力体制を整えましょう。
まとめ
空き家を安全かつ有効に維持・活用するには、法的知識の理解と定期的な点検・対策が欠かせません。
所有者の方は、リスクを理解したうえで適切な行動を早めに取ることが大切です。
空き家を放置することは、所有者のみならず周囲の住民や自治体にも大きな影響をもたらすため、早期の対策が重要です。
建物の老朽化による倒壊や治安の悪化、特定空き家の指定による行政処分、さらには損害賠償リスクなど、見過ごせない問題が数多く潜んでいます。
管理と活用の両面から情報を集め、自治体や専門家の力を借りながら、最良の選択肢を探ることをおすすめします。
空き家について相談するなら「タウンライフ空き家解決」!

空き家について相談するならタウンライフ空き家解決というサイトがおすすめです。
なぜおすすめなのかというと、
あなたの空き家に合った解決方法を無料で診断してくれる上に、具体的な解決プランまで複数の空き家関連企業から無料で手に入れることができるからです。
とりあえず、まずはかんたん1分入力でタウンライフ空き家解決を使ってみてください。
空き家のお悩みは
タウンライフでまるごと解決!

\かんたん1分!ベストな空き家解決策とは?/